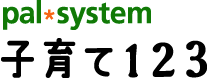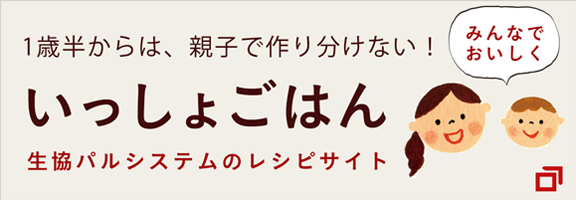子どもたちの五感を開く“味覚”の役割
「オテル・ドゥ・ミクニ」オーナーシェフ 三國 清三(みくにきよみ)
味覚を育むことは、子どもたちの脳の発達や感性を磨くことにつながっている、とフレンチの巨匠であり、食育として「味覚の授業」にも取り組んでいる三國清三さんは語ります。子どもの成長と味覚との関わりを伺いました。
味覚が子どもの感性を磨く

小脳は8歳頃で、大脳は12歳頃で完成すると言われていて、その頃までにどのくらいたくさんの刺激を与えたかが、脳の発達にとってとても重要だと言われています。
いろいろな味を感じることで脳が刺激されると、僕らに本来備わっているはずの、「見る」「聞く」「嗅ぐ」「触る」「味わう」といった五感が開花します。そして開かれた五感を駆使して、周囲や相手をよく観察できるようになるのです。1974年にフランスで味覚の授業を考案したジャック・ピュイゼさんは、「12歳までに基本の味をきちんと体験していない子どもは、成長してから問題行動を起こしやすい」という研究結果を発表しています。友だちを見て、悲しそうだったらなんで悲しいのだろう、うれしそうだったら何でうれしいのだろうと、感性が磨かれた子どもは自然に想像力が働くようになる。味覚を通して五感を磨くことで気づく力が育まれるのです。
味覚を鍛えるのは、自然の味だけ

甘味、塩味、酸味、苦味、うま味の5つの基本の味は、舌にある器官「味蕾」でキャッチします。味覚を鍛えるためには、できるだけ自然の素材を生かした食べ物を選ぶことが大事です。自然界のものはすべからく薄味ですよね。その繊細な淡い味のなかから基本の5味を見分けていけるように、味蕾の数が増えていくわけです。
逆に、自然でない食べ物は、おなかは満たしますが味覚を鍛えてはくれません。化学的に作られたものが入ってくると、味蕾は本能的にぱっと閉じてしまうそうです。自分の身を守るために、そのようにDNAに組み込まれているのかもしれませんね。とくに小さな子どもは何を食べるか選べませんから、親がきちんとした知識をもって選んで与えることが必要です。
家族で食卓を囲んで、たくさんの味体験を

子どもは黙っていても甘いものは食べますが、酸っぱいもの、苦いものは食べたがらないものです。それはもともと「苦いものは毒」「酸っぱいものは腐敗」と、本能的に避けるように刷り込まれているから。どうせ食べないからと、食卓に出すのをやめてしまわないことが大切です。そういう味は、積極的におとなから働きかけて、慣れるように食卓に出し続けることが、子どもの多様な味の体験になります。
昔は、ご飯どきにお父さんが、「今日のみそ汁、味がいいね」とか「そろそろサバか」とか言うのを、子どもたちは何となく聞いていて、「そういうものか」と自然に記憶に刻んでいました。苦味も、サンマのはらわたをうまく隠して食べさせて覚えさせたりしたのです。家族で同じものを食べて同じ時間を共有する。そういう味の記憶が、僕らの心や生活を豊かにしてくれるんだと思います。