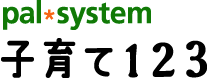嫌いなものを無理に食べさせる必要はありませんが、苦手なものにチャレンジする気持ちを育むのも大切です。
2歳でしたら、「おなかが空いたから食べる」「食べることに関心がむいているから食べる」という時期です。まだ「好き嫌いなく食べると丈夫な体になる」「お皿に載っているものは、全部食べる」などが理解できる年齢ではありません。
食事の時間は楽しく過ごせるのがよいので、苦手なものを無理に食べさせる必要はありません。ただ、食事にかぎらず、苦手なものにもチャレンジする気持ちを育んであげたいもの。例えば苦手な野菜も、調理法や味つけを工夫しながら少しずつ出し続けてあげると食べるかもしれません。また、おとなが同じものを一緒に「おいしいね」と食べることで子どもが食べることも。苦手なものを食べようとしたり、少しでも食べたりしたら、しっかりとほめてあげてください。
食べ物の風味に慣れるまでは、時間がかかります。
子どもの好き嫌いには、その食べ物を食べ慣れておらず、受け入れるのに時間がかかっているという理由があります。また、おとなより咀嚼力が弱いので、かたいだけ、かみにくいだけということもあります。
とくに野菜には、子どもには受け入れにくい風味のものがたくさんあります。たとえば、ピーマンの苦み、ナスの渋みと独特の食感、トマトの酸味、セロリの香りなど、おとなはそこがおいしいと思う特徴が、子どもにはおいしいと感じられないことも。ほうれん草や小松菜などの葉物野菜や、ひじき、しいたけなどの「緑、黒」という色が嫌ということもあります。
これらは経験の差によるもので、繰り返し食べて経験することで、おいしく感じるようになってきます。おいしいと感じられるようになるまでどれくらいかかるかは、個人差があるようです。
食材の切り方や調理方法、味付けなどに変化をつけてみて。
子どもが苦手にしている食材を出すときは、風味をやわらげるような調理をしてみましょう。具体的には、次のような方法があります。
・うまみのある肉、ハム、ベーコン、油揚げ、しらす干し、かつおぶしなどと組み合わせる
・ゆでたり水にさらしてあく抜きをする
・だしをきかせる
・油のうまみを利用する
・小さくきざみ、少量を隠し味に使う
・ごまやのりで香ばしくする
【ピーマン】
色が悪くなるくらいに下ゆでしてから、うまみのある肉などと調理します。
【なす】
水にさらしてあく抜きをし、油で炒めたり揚げたりします。
【トマト】
加熱して酸味をとばします。口に残りやすい皮はむいて。
【セロリ】
少量をほかの野菜や肉と煮たシチューなどに入れて、隠し味に使います。
【ほうれん草や小松菜などの葉物野菜】
やわらかくゆでて短めにきざみ、ごまあえ、のりあえ、ピーナッツあえなどにしてみましょう。繊維が強く残るものは、奥歯の大きさに合わせて1~2cmくらいの長さに切りましょう。
【根菜類】
咀嚼力に合わせて充分加熱して、やわらかくします。
このほかにも、薄くてペラペラしているレタスや白菜、わかめは、加熱してきざみます。皮が口に残る豆、ナスなども、皮をむきます。いもやかぼちゃ、豆のように、口の中がパサパサになるものは、煮物やスープなど水分を残した料理にするとよいでしょう。
保護者の方もいっしょに楽しむつもりで、いろいろな味に挑戦できるとよいですね。
※記事の情報は2021年6月現在のものです。