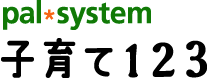地震・災害から赤ちゃんを守るためのQ&A。
危機管理アドバイザー 国崎 信江(くにざき のぶえ)
震災はいつ起こるか分かりません。もしものときにどうしたらいいのか。小さな子どもがいるママの不安に、危機管理アドバイザーの国崎信江さんに答えてもらいました。
目次
備え(備蓄)についてのQ&A
- 備蓄と言われているけれど、どこから手を付けていいか分からない。
- 特別に何かを用意するよりも、まずはいつも食べているものを多めにストックすることから始めてみてください。食べた分をその都度補充していけば、「古くなってしまって、いざというときに食べられない!」ということもありません。
わが家だと、果物をいつも常備しています。果物はそのまま食べられて、水分もあるし、ビタミンもとれるので一石二鳥なんですよ。
- 備蓄していても、子どもを連れているし、持って避難できるか不安。
- 赤ちゃんがいるママへのおすすめは、マザーズバッグへの備え。ふだんから必要最小限のものを入れておいて、災害時にはそれを持ち出せばOKとしておきます。
そうしておけば、赤ちゃんとおでかけ時に被災したときもひと安心ですよね。家の備蓄は落ち着いてから取りに行けば大丈夫です。
【マザーズバッグに入れておきたいグッズ】
- 水ってどれくらい備蓄すればいいの?
- 備蓄する水であれば、一人一日2リットルあれば大丈夫です。
人が一日に必要な水は3リットルと言われていますが、それをすべて飲料水でとっているわけではありません。食事にも水分は含まれていて、1リットルくらいはとれています。保存食は水分がほとんどないので、それだけなら水は3リットル必要ですが、日常食材を災害時にも活用するなら、食材に含まれる水分で補給できます。
非常時には清潔な水がすぐに手に入るとは限らないので、赤ちゃんの粉ミルク用の水は必ず備蓄しておきましょう。殺菌加熱済みの軟水だとそのまま使えますよ。
- 子どもとできる防災対策は?
- 保育園や幼稚園に行っている子がいるなら、いざというときに「パパとママはこういう人です」と見せられるように、園バッグに親の写真を入れて持たせておくといいですね。
子どもには防災ベストもおすすめです。小さなポケットがいっぱいなので出し入れしやすく、走りながらでも取り出せます。キッズ用リュックでもOKです。
水やいつも食べているおやつ、心のケアになる手軽なおもちゃなど、基本は自分のものは自分で持って逃げるというのがいいですね。
そして、周りにいる同じ立場の人に「いっしょにいませんか?」と話しかけること。そうすると自分にないものを相手が持っているかもしれないし、なにより心強い。一人で何とかしようとせず、助けを求めることが大切です。避難についてのQ&A
- ベビーカーは置いて逃げたほうがいい?
- 赤ちゃんと逃げるとき、ベビーカーに乗せての移動はNGです。赤ちゃんはしっかり抱っこをして逃げてください。
ただ、ベビーカーは荷物を運ぶのに便利! 避難所でも赤ちゃんを寝かしつけたり揺らしてあそんだり、何かと重宝します。避難の際は行けるところまでベビーカーに荷物をのせて行き、これ以上進めなくなったときに置いて逃げる、くらいでいいと思います。
- 保育園へはすぐ迎えに行くべき? 仕事で離れた場所にいるので心配。
- 離れているから早く迎えに行くのではなく、むしろ「子どもは保育園にいてよかった」と安心していいと思います。まずは自分の安全を第一に。自分が落ち着いてから子どもを迎えに行くくらいで大丈夫です。
ただ、園によっても震災時の対応はまちまちなので、預け先の防災対策は事前にきちんと確認しておきましょう。
ライフラインが止まっても不便なく暮らせるように災害用トイレ(便袋)、ランタン、掃除用具(ほうき、ちりとり、ガラ袋、ガムテープなど)、蓄電池、発電機なども家庭で備えておくと安心です。 そして自主避難の目安(連続雨量が100mmを超え、かつ時間雨量が30mmを超えたとき)を参考にし、自治体から警戒レベル3が発令されたタイミングで早めに避難しましょう。 小さい子供がいる家庭では避難に時間がかかるので早めに避難することを心がけましょう。
風や雨が強くなる前にバルコニーにあるもので飛ばされやすいものは室内に入れ、念のためサッシにはペットシートなどを挟んで浸水を防ぎます。風が強くなったら窓から離れて過ごしてください。 また、停電に備えて蓄電池を充電し、発電機の燃料を確認しましょう。在宅避難についてのQ&A
冗談のような実話ですが、避難所でミルクが足りず、若い男性職員が1時間かけて歩いて買いに行ったものの、種類があることを知らず、さらに哺乳瓶には乳首が必要なのを知らず、指摘されて何度も買いに行くなど苦労されていました。 広い体育館などにいろんな人が入っているのでプライバシーはない状態です。替えるとしても端のほうでこっそりと、になると思います。 避難所は一時的な場所と思って、家が無事なら帰宅したり、震災疎開をしたりと母子ともにストレスのない環境を選びましょう。 日頃からマンションや地域の人と交流して、声をかけてくれる知り合いを増やすこと。それも子どもを守る防災の備えのひとつですね。 とりあえずのホテル住まいや、アパートやマンションの空き室でも、あとでみなし仮設としてお金が支払われる制度もあるので、まずは少し離れた普通に生活できる場所へ移ってしまいましょう。 とくに都市部は建物倒壊でのアスベスト被害などもあり、赤ちゃんとママの健康を考えると、ライフラインが途絶えたり建物の信頼性がわからない状況なら、迷わずそういう決断をすべきと思います。 震災への不安を少なくするためにも、まずは「知る」ことが大切です。日々の備えだけでなく、インターネットや本でいろいろな情報を得て、子どもを守るための心がまえを身につけていきましょう。 ※今回の記事で挙げているママの疑問は、パルシステム「yumyum club」でのアンケートで寄せられた組合員の皆さんの声を元にしています。 ※記事の情報は2021年8月現在のものです。避難所生活についてのQ&A