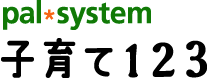子どもなりの表現のひとつです。
子どもが相手を噛んでしまう原因について、愛情不足とか、ストレスといわれることもありますが、愛情たっぷりに育てても噛む子は噛みます。なので、愛情不足を過剰に心配しなくても大丈夫です。
この年頃では、こんなときに噛むことがあります。
- 気持ちを上手に言葉にできない時
- 他の子とどう関わればよいかわからない時
- イライラする時や不安な時
- かまってほしい、甘えたい時
噛みついてしまったら、子どもが落ち着いたあとに優しく理由を聞き、気持ちを代弁してあげます。「嫌だったんだね」「おもちゃで遊びたかったんだね」など、自分の気持ちがわかってもらえると、噛みつきが減る場合もあります。「噛むんじゃなくて『貸して』って言おうね」と、繰り返し教えます。
噛みつきは成長に伴って治ります。根気よく、噛むのはダメなことだと言い聞かせてあげてください。
噛まれたときも、同じように「声かけ」が大切です。
また、自分の子どもが噛んでしまう以外にも、お友だちに噛まれてしまうこともあると思います。そんなときも、噛まれたところをさすったりしながら、「痛かったね」「大丈夫?びっくりしたね」「悲しかったね」など声をかけながら、噛まれた子の気持ちを代弁したり、落ち着かせてあげてください。
どんなときに噛むか、観察することもひとつの手。
相手を噛んでしまう子は、何度も噛むことがあるので、それ自体を未然に防ぐ工夫も必要です。
子ども同士で遊んでいるときは目を離さず、おとなは近くにいるようにしましょう。すぐには難しいかもしれませんが、様子を見ていると、噛みそうになる場面が次第にわかるようになってきます。
たとえば「物の取り合いで噛むことが多いな」と気づいた場合、取り合いが始まってしまったら、噛みつく前に子ども同士を離すようにします。トラブルを解決するのに、「噛む」を選ばないで済む経験をさせてあげるのもひとつの手です。
※記事の情報は2019年12月現在のものです。