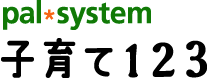鉄分は乳幼児期に大切な栄養素ですが、まずは食事と間食(補食)からが基本です。
鉄分は赤血球のヘモグロビンの成分で、酸素を全身に運搬する働きをします。乳幼児期には脳や神経の発達にも必要な大切な栄養素です。子どもはからだが成長し、血液の量も増加するため、からだの大きさの割にたくさんの鉄分を必要とします。離乳食のときは、鉄分摂取の方法の一つであるフォローアップミルクを取り入れておられたのですね。2歳半になられた現在は、咀嚼力もついてきますし、いろいろな食材に挑戦する気持ちが出てきますので、まずは3食と間食(補食)からの鉄分摂取を基本と考えて、さまざまな食材から鉄分をとるのがおすすめです。
鉄分不足があると、顔色が青白い、疲れやすい、食欲低下などの症状がみられることがあります。子どもは症状があっても訴えることができないので、心配な場合は医師の診察を受け、鉄分不足について確認なさってください。
栄養バランスをととのえ、鉄分が含まれる食材をとりましょう。
栄養バランスをととのえるには、毎回の食事に、炭水化物(ごはん・パン・めん)とたんぱく質(魚・肉・卵・大豆製品)と野菜類(野菜・海藻・いも)の3種類の食材を食卓に出すように心がけます。チャーハンやどんぶりのように1品ものでもかまいません。間食(補食)では、お楽しみのお菓子だけでなく、食事のとき食べていない食材(例えば乳製品やフルーツ)やあまり食べなかった食材があれば取り入れましょう。
鉄分はとりにくい栄養素と言われています。鉄分の推奨量(ほとんどの子どもが不足しない量)は、日本人の食事摂取基準2025年版で、1~2歳児が4.0mg/1日、3~5歳児が5.0mg/1日、6~7歳児が6.0mg/1日と示されていますが、令和5年国民健康・栄養調査では、1~6歳児の鉄分の1日の摂取量は3.9mgという結果が公表されています。鉄分を含む食材を積極的に取り入れましょう。
食材に含まれている鉄分には2種類あります。赤身の肉や魚、レバーなど主に動物性の食品に含まれている「ヘム鉄」と野菜や大豆製品など主に植物性の食品に含まれている「非ヘム鉄」です。鉄分が多く含まれている食材を紹介します。
ほうれん草やレバーなど苦手な食材にこだわらず、下記の食材から食べやすいものを探してみてください。きなこやすりごまが食べられれば、毎日少量ずつ使うのもよいでしょう。
【ヘム鉄を多く含む食品】
そのままでも吸収率が高いのが特徴です。
●まぐろやかつおなど赤身の魚(まぐろ赤身30gに0.3mg、かつお30gに0.6mg)
●肉類の赤身部分(牛赤身30gに0.7mg、豚赤身30gに0.3mg)、レバー(鶏レバー20gに1.8mg…ビタミンAを多く含むので週1回程度に)
【非ヘム鉄を多く含む食品】
そのままだと吸収率は低いですが、いっしょに動物性たんぱく質(肉や魚)やビタミンC(野菜や果物、たとえばブロッコリーやキャベツなど)をとったり、体に鉄分がもっと必要という状態になると、吸収率がよくなる特徴があります。
●大豆製品(豆腐50gに0.6mg、納豆30gに1.0mg、きなこ大さじ1に0.4mg、ゆでえだまめ30gに0.8mg)
●青菜など(ゆでほうれん草30gに0.3mg、ゆで小松菜30gに0.6mg、ゆでブロッコリー30gに0.3mg)
●ごま(大さじ1に0.6mg)
●貝類(あさり5個に0.6mg)
●卵黄(1個分に0.8mg)
鉄分強化の食品を使っても。
鉄分強化の食品を使うのもよいでしょう。牛乳、ヨーグルト、チーズ、ジュース、ウエハースなどの菓子などがあります。食品表示に食べさせ方の注意があれば確認してから使いましょう。鉄分強化の食品だけをたくさん食べさせるようにするのではなく、バランスのとれた食事や間食(補食)のなかで取り入れましょう。
フォローアップミルクは鉄分が強化された食材のひとつとして考えるとよいでしょう。
フォローアップミルクは、調乳すると牛乳と同じくらいのカルシウムが含まれ、牛乳には少ない鉄分、ビタミンDなどが強化された、牛乳の代わりになる粉ミルクです。調乳した100mlのフォローアップミルクには1.1~1.3mgの鉄分が含まれています。
【授乳・離乳の支援ガイド(2019年改訂版)実践の手引き 母子衛生研究会より】
2歳半であれば、1日の牛乳・ヨーグルトなどの乳製品のめやすは、200~400ml(g)です。1日に与える乳製品の範囲で、牛乳のかわりに調乳したフォローアップミルクをコップから飲ませたり、牛乳を使うシチューやポタージュスープなどに入れたり、プレーンヨーグルトに混ぜたり、濃く溶いてパンに塗ったりの利用もよいでしょう。
サプリメントを子どもに飲ませるときは、医師などに相談してからがおすすめです。
サプリメントは、特定の成分を簡単に大量にとることができるので、過剰になると体に悪影響が出る心配があります。サプリメントの種類、量、摂取期間を医師などに相談してからの使用をおすすめします。
【参考】
「日本人の食事摂取基準2025年版 厚生労働省 」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44138.html
「令和5年国民健康・栄養調査の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf
授乳・離乳支援ガイド(2019年改訂版)実践の手引き 五十嵐隆監修 母子衛生研究会
日本食品標準成分表2020年版(八訂) 文部科学省
※記事の情報は2025年3月現在のものです。