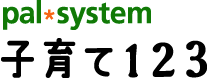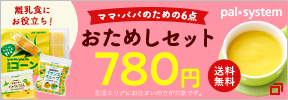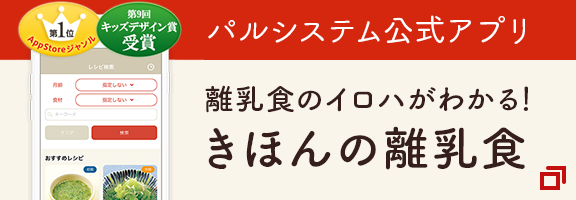抱きぐせという言葉は、死語になりつつあります。
私もときどき、若いお母さんが年配の方からそう言われる場面に遭遇します。産院では「泣くたびに抱っこしてください」とか、「抱きぐせはない」ともいわれるので混乱しますね。では、どうして赤ちゃんは泣くのでしょうか?
0~1カ月頃は、生きていくためです。おとなに世話をしてもらおうと泣いて知らせます。3カ月頃を過ぎると、それ以外にも甘えたい、かまってなどの理由で泣くようになり、抱っこで「心」が落ち着くようになります。
研究によって、人は抱っこされ、あやされ、ふれ合うことで、オキシトシン(別名:愛情ホルモン)が出ることがわかってきました。乳幼児期にたっぷりふれ合うことで、その後の発達が安定するとも言われています。「抱きぐせがつくから抱っこしない」という言葉はすたれ、死語になりつつあります。
とは言え、ひとりで四六時中抱っこしているとほかのことができません。もしかしたら人手がないときに、親が罪悪感を抱かないように「抱きぐせ」という言葉が生まれたのかもしれませんね。